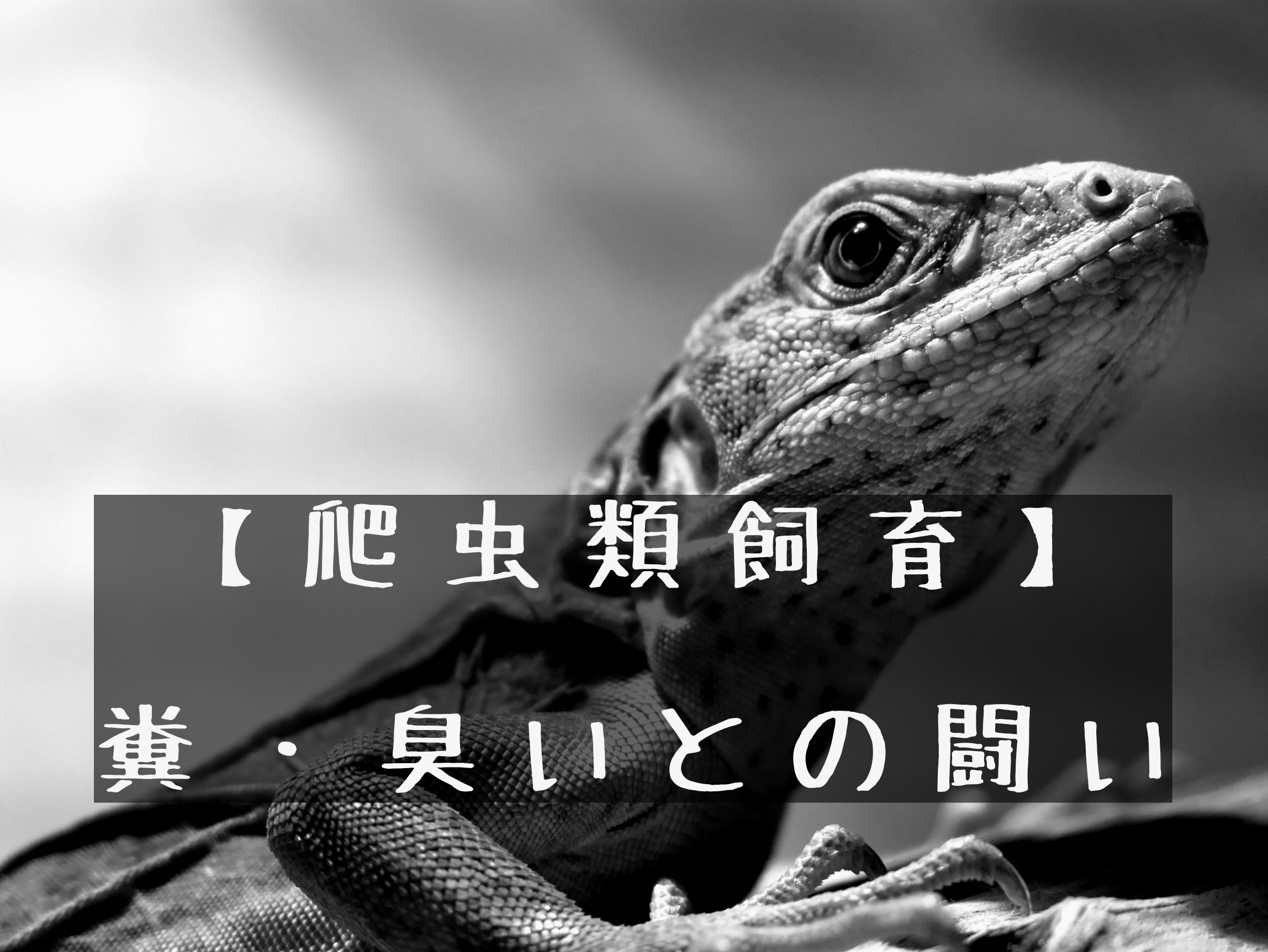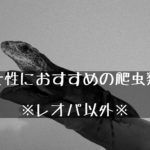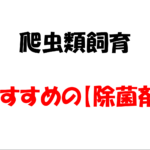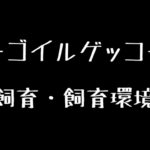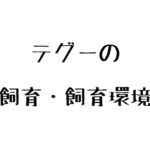【51Base】です.
【爬虫類飼育】糞・臭いの原因と対策
この記事をご覧になられている方の多くは爬虫類飼育者,もしくは飼育を検討されている方かと思います.
爬虫類だけではなく,生物を飼育するということは糞の処理をするということだと思っています.
よく飼育を開始した後で
臭いのすごさにびっくり
される方も多いかと思いますし,飼育前は生体の飼育環境や慣れるのか,エサは,電気代はなど飼育面での情報を追いがちですよね.
でも実際飼育してからのメンテナンスについてはあまり調べることがないかもしれません.
ですので,今回はそのメンテナンスの中で多くを占める糞の処理について実際に私が行っている対策や方法,自己考察も交えてまとめていこうと思います.
目次
1.なぜ糞は臭うのか?
そもそもなぜ糞は臭うのでしょうか?
一般的に食物が腐敗・発酵した臭いと言われていますが,ほとんどは細菌類の臭いです.
肉食性の動物は草食性の動物と違い消化する脂質・蛋白質が圧倒的に多くなり腸内での消化酵素は多い傾向があります.
その為,消化酵素が多い分臭いも強く,発酵した腐敗臭のような生臭さも出ます.また,哺乳類などではそうですが,縄張りのマーキングの一つとも言われています.
また草食性の動物については糞内に窒素が非常に多く含有されています.
これが糞性菌の子実体形成に非常に有利に働くため,腐敗が進む前に菌類による分解が促進されていきます.
動物の糞上に出現する菌類の総称です.実は多くの菌はその生命を動物の糞に依存しています.糞内容物にある窒素や有機物,消化器内の粘液などいわゆる菌のエサとなる物質がとても多く含まれています.これらを分解し成長し,胞子を飛散させ繁殖していきます.
臭いについてはやはり臭くない方が良いでしょう.ですが,人間の体もそうですが基本的に排泄物は健康のバロメーターです.
生体の糞の臭い,形,水分量など必ずチェックするようにしましょう.
2.爬虫類の糞は臭い?
よく爬虫類が臭いなんて話を聞きますが
生体そのものは臭いません.
爬虫類は基本的に臭腺がないからです.
なので人間やその他哺乳類の様なアンモニア臭などもありません.ですが,やはり糞は臭いがあります.
これはどの生物にも共通していることです.
■肉食性の糞の臭い
肉食性,雑食性の爬虫類は共に糞の臭いはなかなか強烈です.哺乳類などのアンモニア臭というよりは淀んだ生ぬるい臭いといった感じです.
特に臭いが強烈だなと感じる種類は…
・モニター全種(特にミズオオトカゲ)
・アオジタトカゲ
・フトアゴヒゲトカゲ(成体)
この3種は特に臭いが強いですね.
爬虫類の臭い対策についてはこちら↓↓↓ https://chosyucrypter.com/archives/14927620.html
パイソン・ボアについては排泄サイクルが比較的長いのでなんとも言えませんが,特定クラスのサイズは当然糞の大きさも特大ですのでかなり臭いです.
後はナミヘビ系は排泄のサイクルが早いため,糞・尿の頻度は多いです.
アオジタトカゲとフトアゴヒゲトカゲは肉食性の強い雑食性のトカゲです.
基本的に爬虫類は臭腺がありませんので,ほぼ無臭です.
臭いのほとんどは糞尿で,体に糞がついてしまえば当然,生体は臭くなってしまいます.
肉食性のトカゲに限らず,肉食の生物は全体的に糞生菌と呼ばれる菌類が少ない傾向にあります.
この糞生菌は主に糞の分解を担っているとされ,その役割は生物によって違いがあるようですが,概ね草食性の動物には多く発芽する傾向があります.
肉食性のトカゲには粘状で水分も多く糞生菌が少ない為,草食性のトカゲよりも分解の処理能力が低く,発行しやすいため臭いが強いといった傾向があります.
■草食性の糞の臭い
草食性の爬虫類となるとリクガメとイグアナ科くらいです.彼らの糞は総じて臭いは少ないです.形状としても細長いような糞で,割とすぐ乾燥します.
ただ尿は少しアンモニア臭が強い印象があります(イグアナ科).
草食性の場合は糞中にも植物性の窒素含有量が多いため糞性菌の出現が多いとされていますし,草食動物の糞性菌の発生は似通っています.
また草食性の爬虫類の方が糞の頻度は比較的早いものが多いです.
パイソンやボアなどは消化にすごく時間を要しますが,肉食と草食のトカゲで比較すると恐らく草食のトカゲがわりと糞の頻度は早いはずです.
また草食のトカゲはセルロースを分解する腸内細菌を多く持っていますが,セルロースは分解が困難です.
そのため,未消化の有機体として糞が多く排泄される傾向にあります.
またこの有機体が多く存在することが糞性菌の発生を促し,発酵・腐敗が起きる前に分解されるものと言われています.
3.爬虫類の排泄サイクル
爬虫類の排泄サイクルを語るうえで最も大切なことは
「変温動物」
であることだと思います.消化・吸収には非常に多くの熱量(エネルギー)を使用します.
その際,体温は上昇します.この体温の上昇を爬虫類は外的要因に頼らざるを得ません.
まず大前提として適切な温度管理がされている事として少しまとめていきます.
■尿酸
爬虫類における尿酸とはタンパク質の代謝によって生じる有機体,窒素化合物のことです.人間の場合は尿として排出しその尿中の窒素化合物は尿素となります.
爬虫類は総排泄孔とよばれる部位から尿酸と糞を排出します.
もちろん腎臓にて濾過されたものが尿酸となり総排泄孔へ蓄積され排出されるのですが,タンパク質の過剰摂取は尿酸の処理能力を超え痛風や膀胱結石,便秘を引き起こしかねないため,適度な広さのケージとエサの過剰摂取には注意が必要です.
4.糞の臭い対策
■各種臭い対策
各種における糞対策を簡単にまとめていきます.
・ヘビ全種の糞と臭い対策
ペットシーツ使用によりある程度の消臭効果あり.そもそもニシキヘビは消化サイクルが遅い傾向にあり糞もベビー~ヤングで週1~2回,アダルトは2-3週に1回程度.
・イグアナ科の糞と臭い対策
グリーンイグアナは自身の糞で体が汚れることを嫌います.体に糞が付かないような場所を設けてあげるとそこで糞をすることを覚えます(個体差あり)
・フトアゴヒゲトカゲなどのアガマ科の糞と臭い対策
温浴で対応可能.温浴時に排泄する個体が非常に多い.毎日決まった時間に温浴をするようにすると概ねその際に排便をするようになります.

・モニター全種の糞と臭い対策
大型のアダルト個体までいくと糞をする場所が特定されますが,基本的に対策としてはこまめに掃除しかないです.
ミズオオトカゲなどはかなりの確率で水容器で糞をしますので,水容器を交換するだけで良いです.
ただし,糞まみれの水にも平気で入りますので,生体そのものが臭くなることもあります.定期的に温浴させてあげましょう.
ツリーモニター系は諦めましょう
・ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の糞と臭い対策
かなりの高確率でトイレを覚えます.覚えるというよりは糞の匂いが残っている所に糞をする傾向がありますので,その場所に簡易的なトイレを作ってやればいいです.
トイレといってもすぐに処分できるようなキッチンペーパーなどで良いでしょう.
その他人工餌を使用してみると臭いが軽減されたという方もいらっしゃいます。
・クレステッドゲッコーの糞と臭い対策
グレイテッドゲッコーの臭いはなかなか強烈で、大型の爬虫類に匹敵するほどです。 なので、まずはグレイテッドゲッコーが糞をした場合は、こまめに取り除くことです。
その他に、餌などを昆虫ゼリーにしたり、消臭パウダーを床材に混ぜる事で臭いを抑えることができます。
■床材
一般的に使用されている床材は,ウッドチップやサンド系のものが多いのではないでしょうか.ヘビなんかではペットシーツを使われている方も多いかと思います.こちらのような床材を使用している場合は目安として大型の爬虫類で2か月、小型の爬虫類で4か月くらいで床材全体を交換する方がいいでしょう。
昨今は床材にも消臭効果を謳った商品が多く発売されています.
最も大切なことはこまめな掃除かと思うのですが,日中働かれている方がほとんどでしょうからメンテナンスも大変ですよね.
モニターやイグアナ系を飼育する場合,私はよくベランダなどで用いられるジョイントタイルや人工芝を好んで使用しています.
モニターなど爪の鋭い種は定期的に爪切りをしなくてはならず,その度に前腕は悲惨なじょうたいになります.こういったジョイントタイルを用いれば程よく爪も伸びない為,重宝しています.
またこのタイルの下にペットシーツを敷くこともできるため,糞尿と一緒に排出された水分も吸収してくれますので,匂い対策としても良いかと思います.
*ペットシーツは大量購入後にストックしていた方がお得です.私は薄型の方が見た目的にもスマートですので好んで使用しています.吸水性も良好です.
人工芝についても同様で,下にペットシーツを敷けるだけでなく,安価で汚れがひどくなってくれば交換すればいいですし,糞をした部分だけ取って洗えば結構長く使えます.
*爬虫類の臭い対策についてはこちら↓↓↓

ただ両者ともに下に敷いたペットシーツがある程度消臭してくれますが,便はそのままの状態ですので,やはりまめに掃除をすることが肝要です.
また,爬虫類専用の消臭剤も販売されています.発売されて結構立ちますが未だにBESTグッズだと思っていますので,まだ使用されたことのない方はぜひお試しください.
5.まとめ
いかがでしたでしょうか.
爬虫類飼育をするうえで必ず必要なメンテナンスで多くを占めるものがこの糞の処理だと思います.
糞の処理・匂い対策については各飼育者によってその方法は千差万別でSNSなどでも
「その手があったか!!」
と驚かされることも多々あります.
対策としては
・糞の処理や食べ残しの処理をすぐに行う
・エサを変えてみる
・床材を工夫する
・消臭スプレーを使用する
・お掃除をこまめにする
が有効かと思います。
今回ご紹介した糞の臭い対策についてもごく一例に過ぎないかと思います.ぜひ飼育者一人一人が生体と飼育環境,そして生活環境に合った方法を探し出してみてください.
それも一つの爬虫類飼育の醍醐味なのかもしれません.
**生き物を飼育することの是非はここでは問いません.また,本記事は飼育を促進するためものではありません.
生き物を飼育することは命を預かることです.その生体を最後まで責任を持って飼育することが飼育者の義務です.飼えなくなったという理由で逃がしたりすることは絶対にやめましょう