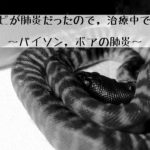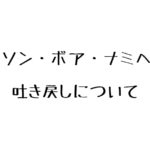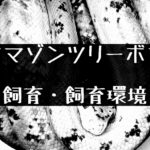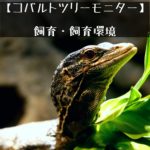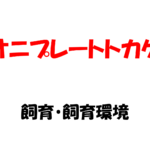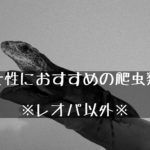【51Base】です.
【ウォータードラゴン・ホカケトカゲ】
飼育・飼育環境
ここ数年で爬虫類イベントやショップ,カフェなど徐々に爬虫類の人気が高まってきています.
もちろん,生き物を飼育することに流行などあってはいけないと思いますが,こうして少しずつでも爬虫類の良さに気づいてくださる方々や,飼育者が増えていることは個人的にはとてもうれしく思います.
さて,今回は熱帯雨林に生息する樹上棲かつ水生の傾向も強い
「ウォータードラゴン・ホカケトカゲ」
本種たちは幼体時こそ非常に愛らしい姿をしていますが,成体の特にフルアダルトとなったものなどオオトカゲすら凌駕する大きさとカッコよさを兼ね備えています.
毎年コンスタントに東南アジアから輸入があり,価格的にも安価である本種のベビーですが意外に成体はあまり見かけないような気もします.
今回はそんなウォータードラゴン・ホカケトカゲの生態と飼育環境などについてまとめていきます.
目次
1.分類と生態
■分類
□ウォータードラゴン
 参照:Wikipedia
参照:Wikipedia
爬虫網有鱗目アガマ科ウォータードラゴン属
□インドシナウォータードラゴン
□ヒガシウォータードラゴン
(ヒガシウォータードラゴンはオーストラリアの固有種ですので,海外で殖やされたもしくは国内CB個体しか出回りません)
□ホカケトカゲ

爬虫網有鱗目アガマ科ホカゲトカゲ属
□アンボイナホカケトカゲ
□フィリピンホカケトカゲ
□ハルマヘラホカケトカゲ
□セレベスホカケトカゲ
□マカッサルホカケトカゲ
市場でよく目にするものはアンボイナホカケトカゲでしょうが,いずれにしてもベビーが大量に輸入されてきており,育った個体を見る機会は少なく感じます.
*似た生体で「バシリスク」といったトカゲがいますが,アガマ科ではなくイグアナ科になります.
【ホカケトカゲ】帆掛蜥蜴《属》
— 動物図鑑 (@animalsinjapan) October 18, 2024
[分類]爬虫類有鱗目アガマ科
[体長]最大1m
[分布]スラウェシ島、モルッカ諸島、フィリピン
[生息域]森林の樹上
[餌]葉、果実、昆虫類
アンボイナ、フィリピンなど5種。全長の3分の2は尾。尾に帆のような鱗がある。泳ぎも得意。 pic.twitter.com/lF18pLiYDO
■生息
□インドシナウォータードラゴン
中国南部~カンボジア・タイ・ベトナム
□ヒガシウォータードラゴン
オーストラリア東部
□ホカケトカゲ
インドネシア・フィリピンの島々

上記のヒガシウォータードラゴンは私がオーストラリアで野生の生体を撮影したものですが,町中の公園にいたものです.
夢中でシャッターを切っていると,「何が珍しいんだ?」と現地の人に笑われた記憶があります.
いかにオーストラリアで日常的に目にする生体でもやはり固有種というものは厳重に保護されているのだなと実感した瞬間でもありました.
■大きさ ・ 価格
□インドシナウォータードラゴン
全長:60-90㎝
最大全長:100cm
価格:5000円~10000円
□ホカケトカゲ
全長:80-100㎝
最大全長:120㎝
価格:5000円~40000円
インドシナウォータドラゴンは比較的小柄ですが,オスの生体は頭部から背部にかけて長いクレストを形成するので非常に迫力があります.
ホカケトカゲはその独特なフォルムから一度目にすれば忘れることはできないかもしれませんね.
アガマ科では最大種となります.
2.飼育環境
■飼育ケージ
本種は樹上棲の傾向が強く,基本的には高さのあるケージが必要となります.
高さのあるケージはなかなか選択肢が少なくなりますが,幼体時はグラステラリウムで対応は十分可能です.
最終的には自作ケージが必要になるでしょうが,インドシナウォータードラゴンについては既製品のケージでも飼育は十分可能です.
かなり大掛かりなケージとはなりますが,横幅が120㎝でかつ高さが60㎝ほどありますので,ケージレイアウトをしっかり行えば成体の飼育も可能です.
ホカケトカゲに関しては平均でも1mは超えてきますので,自作ケージを作製することをおすすめします.
モニターなどと比較しても体の柔軟性は劣りますのでかなり広めのケージが必要となります.
■爬虫類の自作ケージについて
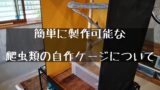
■温度・湿度
東南アジアは熱帯性気候にあたりますので,基本的には高温多湿な環境です.

参照:地球の歩き方
上記がインドネシアの年間の気候になりますが,年中通じて寒暖差がほとんどなく,あるとすれば降水量でしょうか.
また,熱帯雨林は木々が生い茂っているため,砂漠や草原地域と比較して昼夜の寒暖差もなく夜間も25℃を下回らないことが多いです.
|
最高気温 |
最低気温 | |
| 日中 | 30-35℃ | 28℃ |
| 夜間 | 28℃ | 25℃ |
また湿度についても同様に,60%は下回らない方が良く,基本は80%.
特に日本の冬は湿度が非常に低下しますので,その環境下でケージ内を保温すると間違いなく湿度は40%を切ります.
乾燥した環境に適応していない彼らにとってそれはストレスの原因ともなりますし,呼吸器系の疾患を患うとも言われていますので湿度管理は厳密に行いましょう.
■冬期の保温には暖突が消費電力的にもオススメです
(Lサイズは消費電力も抑えられています)
■暖突を使用する際には必ずサーモスタットを使用してください.
■爬虫類の湿度管理について

ここ2.3日‥体調悪くて撃沈してた(꒪ཀ꒪*)
— NARS࿊ (@NARS89050076) October 11, 2024
いつも無口なのに気にかけて来てくれた優男(๑ ˊ͈ ᐞ ˋ͈ )キュン
脱皮中のゴジラ///
この後、いつも寝とる場所に移動して寝た(¦3ꇤ[▓▓]#ホカケトカゲ pic.twitter.com/O89ZU69I4x
■紫外線
基本的に昼行性のトカゲに紫外線は必須と考えています.
モニターなどは捕獲した獲物からビタミンD3を得ることが出来るため紫外線は必要なく,レフ球のみでの長期飼育が可能といった話も聞いたことがありますが,正直まだわかっていないことも多いです.
では本種はどうかといわれると主食が昆虫食となる幼体時は必ず紫外線の照射は必要と思われます.
逆に成体時は魚などを捕らえていることが分かっていますし,小さな哺乳類なども捕食しますので,そこからビタミンD3は摂取できているかと推察されます.
しかし,自然界で大いに紫外線を浴びているため,飼育下でも可能な限りその環境は再現するべきではないでしょうか.
必要量については砂漠に生息するアガマ科よりは少なくとも問題ないです.
欲を言えばメタハラですが,非常に高価ですので最近はセルフバラスト水銀灯も非常に紫外線量が多い為,そちらを使用しても良いと思います.
■セルフバラスト水銀灯ではこちらの3つが主力です↓↓↓
■メタハラは高価ですが資金的余裕があればぜひ導入したいアイテムです↓↓↓
生体の発色を上げる場合はしっかりと紫外線を照射するようにしましょう.
■爬虫類の紫外線について

■水容器
本種は樹上棲の傾向が強い一方でほとんどが水辺の木の上で生活をしています.
これは天敵に襲われたときに素早く水中へ逃げることと,エサである昆虫や小魚が豊富にいるからです.
飼育環境でもぜひ大きな水容器を用意していただきたいところですが,いっそのことケージの床面に水を張っても良いかと思います.
メンテナンスはその水をホースで吸い上げて入れ替えるだけで良いですし,オーバーフローシステムを導入されている方も見たことがあります.
風呂入りながら寝てるw#ハルマヘラホカケトカゲ#ホカケトカゲ pic.twitter.com/lXKtLJDXtj
— Pさん (@48Papaiya) February 1, 2024
3.エサ
■ウォータードラゴン
本種は非常に肉食傾向の強い雑食性です.グリーンイグアナのイメージを重ねられる方もいらっしゃるかもしれませんが,本種は彼ら以上には野菜は食べません.
人工飼料に餌付くものもいますが,基本的にはコオロギやデュビアなどの無脊椎動物を中心に与えてください.
その際にダスティングは忘れないようにしてください.
*ビタミンD3入りのものは過剰摂取に注意が必要なのでできれば2つ用意できていれば良いです.
個体によっては活き餌にしか反応しませんが,環境に慣れてくると乾燥コオロギなどにも餌付くものもいます.
栄養面でビタミン不足が懸念されますが,管理は非常に楽になります.不足しているビタミンについては適宜サプリメントなどで補っていきましょう.
成体時には葉野菜やニンジンなどの根野菜も食べますが,イメージ的には果実には食いつきが良いです.(というより私は葉野菜を食べている所は見たことがありません)
ほぼ完全肉食性なのではないかとも疑うほどですが,食べる生体は食べる様です.ただし食べたとしてもメインではなく3割程度でもいいでしょう.
■ホカケトカゲ
雑食性で幼体時は特に好んで昆虫類は食べる印象で,小松菜などの葉野菜から果実も食べます.
バナナは割と食いつきが良い印象です.
個体によってはイグアナフードなどに餌付くものもいます.
ですが,やはりメインは葉野菜やニンジン,豆類,食用タンポポなどを与えるようにします.
また,野生下では魚を獲物としていることもわかっていますので時折魚や,小さなげっ歯類を与えても良いです.
恐らくこの時の食いつきは素晴らしいものがあると思いますので,ついついまた与えてしまいたくなりますが過度な給餌は肥満となり短命になってしまいますので,エサの管理については厳密に行いましょう.
ホカケトカゲは1日ぶり、インドシナは2日ぶりの給餌でこれくらいの食い付きです。生き餌ならもうちょいがっつきいいかもです。
— Ariboreal (@Ariforsyth) February 27, 2019
エサはグラブパイです!!#インドシナウォータードラゴン#ハルマヘラホカケトカゲ pic.twitter.com/GByKynUeBn
4.ハンドリング

インドシナウォータードラゴンは比較的温和な性格をしているものが多いので,積極的に噛んでくるものは少ないと思います.(上記の写真はホカケトカゲ)
ただし個体差はもちろんあることと,ベビーで購入直後は概ね逃げ回るものがほとんどです.
ケージ前を通っただけでバタバタといったことも.これはホカケトカゲにも言えることですが.
ただし,モニター・オオトカゲと比較すると力はそこまででもなく,体も硬いので振り向きざまに首を180°曲げて噛んでくるといった離れ技はしてはきません.
■オオトカゲ・モニターの慣らし方
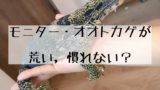
購入直後はまず環境に慣れさせてあげてからと考えた方が飼育者も生体も余計なストレスが掛からずに済みますので,まずは焦らないことです.
よくSNSなどでベタ慣れの生体を目にすることも多いと思いますが,ある程度時間を掛けたものがほとんどですので,最低でも半年くらいは時間を掛けて慣らしていければ良いのではないでしょうか.
5.まとめ
いかがでしたでしょうか.
【ウォータードラゴン・ホカケトカゲ】
飼育・飼育環境
ベビーは比較的よく目にしますが,意外にも成体はあまり見かけない本種ですが,成体の姿は他の大型爬虫類の追随を許さないほど魅力的な姿をしています.
ぜひ最高の飼育環境にてしっかりと育て上げて,本種の魅力を最大限に引き出してください.
**生き物を飼育することの是非はここでは問いません.また,本記事は飼育を促進するためものではありません.
生き物を飼育することは命を預かることです.その生体を最後まで責任を持って飼育することが飼育者の義務です.飼えなくなったという理由で逃がしたりすることは絶対にやめましょう










































































![[OMEM] 動物用ハンドリング手袋 フルレザーか み傷防止 爬虫類 ヘビ トカゲ 傷耐性保護手袋エクストラロング 58CM](https://m.media-amazon.com/images/I/51R54IeoPhL._SL160_.jpg)